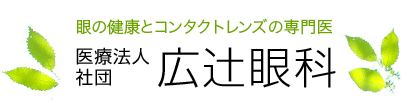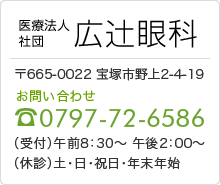花粉症いろいろ
院長 廣辻徳彦
花粉症についてマンスリーでは何回か書いてきましたが、今や日本人の3-4人に1人が花粉症らしく、「国民病」と言われるようにもなっています。今回は眼科的治療というより、花粉症が経済に与える影響や仕組みと眼だけに限らない対処法などをまとめてみます。
調べてみると、パナソニック株式会社が「花粉症による労働力低下の経済損失額2024」というものを推計しています。花粉症の人の約8割で症状が自身の仕事のコンディションに影響していたり、花粉症により仕事のパフォーマンスが1日のうち平均で約2.8時間低下していると感じたりしているというアンケートの回答があったそうです。これと民間給与実態統計調査(国税庁)や労働力調査(総務省統計局)を元にして計算すると、経済損失額は1日あたりで「約2,340億円」に該当するということです。1年に換算すると85兆円余りとなって国家予算くらいになりますが、別の報告では約5兆円というものもあるので、花粉症のシーズンで1日あたりというものなのかもしれません。こういう推計は、それだけ花粉症が問題になっていることを示しているのだと思います。
花粉症は主に鼻と目に症状が現れますが、医学用語的には「季節性アレルギー性鼻炎」のことをいい、花粉が飛ぶ季節に始まる「くしゃみ、鼻水、鼻づまり」というアレルギー症状のことを指します。目の症状としては、「かゆみ、充血、涙」が挙げられます。それ以外にも体がだるい、熱っぽい、イライラする、喉や顔、首がかゆい、十分な睡眠が取りにくい、集中力が低下するといった全身症状を伴うこともあります。
アレルギーは体内の免疫システムによって引き起こされます。花粉が目や鼻から入ってくると「異物=敵」とみなされます。花粉の中にある抗原物質にマクロファージという細胞が反応して、その情報をリンパ球のT細胞へ送り、さらにB細胞がそれに対抗するための「IgE抗体」というものを作ります(初めてこのような反応が起こることを「感作:かんさ」といいます)。このIgE抗体はその花粉専用の抗体(特異的IgE抗体)で、次に花粉が入ってきたときに肥満細胞という細胞に働きかけて、ヒスタミンやロイコトリエンという化学物質を放出させて粘膜を刺激し、くしゃみや鼻水、涙を出すことで花粉を体外に出すように働きます。この反応自体は異常なものではないのですが、抗体は花粉に接触するたびにつくられるため、少しずつ体内に蓄積されていきます。蓄積量が一定量を超えるレベルに達すると、次に花粉が入ってきたときに過剰なアレルギー反応=花粉症を起こすようになり、くしゃみが止まらない、痒みなどの症状がずっと続くということになります。また、粘膜内では好酸球という細胞が多くなります。この好酸球が上皮細胞を刺激することでも過敏な状態が引き起こされます。花粉症の診断のために、鼻汁や結膜での好酸球の増加を顕微鏡で確認したり、血液検査で好酸球の割合の増加や特異的IgE抗体の量を測定したりします。
治療は症状を抑える対処療法と反応自体を抑える棍治療法があります。対処療法には点眼薬、点鼻薬による局所療法、内服薬を使用する全身療法、鼻粘膜に対してはレーザー治療もあります。薬剤は抗ヒスタミン薬(第一世代、第二世代)、抗ロイコトリエン薬、化学伝達物質遊離抑制薬などの抗アレルギー薬の内服薬や点鼻薬、点眼薬、そして局所ステロイド薬の点鼻薬、点眼薬、内服薬を組み合わせます。抗アレルギー薬は症状のある時だけでなく、毎日使用する方が効果を得られるので指示通りに使ってください。棍治療法には原因となる抗原を薄い濃度から注射などで身体に反応させ、徐々に高濃度にしてそれに対する過敏性を鈍くさせることを目的とした減感作療法があります。
抗原物質の回避や除去も有効です。花粉の飛散量は昼前後や夕方に多いらしいのでできればその時間帯を避け、外出のときはマスク(不織布:感染症にも有効)やメガネの着用をします。コンタクトレンズはマイナスに働きます。服装はウール素材より綿、ポリエステルなどの花粉が付着しにくい衣類で、帽子も有効です。建物に入る前に衣類の花粉を払い落とす、帰宅後のうがいや洗顔、洗眼(カップ型は避ける)、シャワーを浴びるのもありです。洗濯物の外干しを避け、シーツやカーテンなどにも掃除機をかけると花粉やハウスダストを減らすことができます。政府も植林で増えたのに使われていないスギ人工林の伐採や植え替えを行い、飛散予想への情報提供をしているそうです。この時期本当に厄介な花粉症ですので、十分な対策をお願いします。