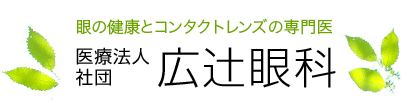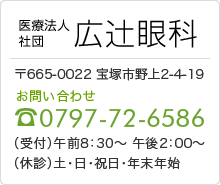近視の抑制治療
院長 廣辻徳彦
最近のマンスリーで、近視進行抑制点眼薬(リジュセア・ミニ)やオルソケラトロジーについて紹介してきました。近視は緑内障や網膜剥離、網膜脈絡膜萎縮や近視性新生血管黄斑症など、さまざまな重要な病気のリスクを高めます。近年子どもの近視の発症は低年齢化して近視の人の割合が増加してきているので、近視の抑制に注力することが世界的な問題となっています。わざと緩めのレンズを使う低矯正眼鏡、ピンホール眼鏡、ブルーライトカット眼鏡、二重焦点眼鏡(累進屈折力レンズ眼鏡などを含むいわゆる遠近両用眼鏡)、一般の単焦点コンタクトレンズ(以下CL)などに近視進行抑制効果は確認されていません。5年前に記事にした時は若干懐疑的な内容でしたが、今回は効果のエビデンスがある方法について紹介します。ただ、今はすべて保険外の自費診療で、しかも長い間続ける必要があるので、数十万円以上の費用負担が問題となります。(今回は日本近視学会のHPを参考にしました。)
1)低濃度アトロピン点眼液
5月にも紹介しましたが、厚労省に承認された点眼薬が今年参天製薬から販売されました。もともと、アトロピンという薬は副交感神経の作用を抑制する働きを持ち、胃腸の痙攣性疼痛、胆管・尿管痛、徐脈、有機燐系殺虫剤・副交感神経興奮剤の中毒(サリン中毒など)、麻酔前投薬などに使われ、眼科でも1%点眼薬として小児の斜視や弱視の診断や治療に用いられてきました。低濃度の0.01%~0.05%アトロピン点眼を1日1回点眼すると、近視の進行を30~70%抑制する効果があることがわかってきています。副作用が少なく手間がかからない反面、途中でやめた場合にリバウンドという抑制されていた近視が進みやすくなる可能性も指摘されています。
2)近視管理用眼鏡
ここでは詳しい理論の説明はしませんが、近視の進行抑制のために「周辺部の網膜に、網膜の手前でピントが合う光をたくさん作用させるのが有効」というデフォーカス組込み理論に基づく多分割眼鏡レンズ、「周辺部の網膜のコントラストを下げることが有効」というコントラスト理論に基づく低光線拡散レンズという近視管理用眼鏡が開発されています。2018年ごろから海外で販売されているこれらの近視管理用眼鏡は、通常の眼鏡などと比べて55%〜60%近視の進行を抑制することが報告されています。5-7歳くらいで装用し始め、成人するくらいまで続けて終日眼鏡をかける必要がありますが、子供でも比較的容易に実施することができ、リバウンドが報告されていないのもメリットです。
3)多焦点ソフトCL
多焦点ソフトCLは、一般には遠用の度数に近用の度数が加入された、老視(老眼)矯正のための遠近両用CLが使われています。 海外では様々なデザインの多焦点ソフトCLが子どもの近視進行抑制用に開発、販売されています。日本で国内臨床治験が終了し、近視進行抑制治療として厚生労働省に承認申請中のCLは 、近視進行を52-59%抑制することが示されています。このCLは1dayタイプのため、衛生面での管理は比較的容易です。ただ、CLのはめはずしなどの自己管理が可能な年齢になるまでは使用できないため、小学校高学年以降の小児が対象となります。
4)オルソケラトロジー
オルソケラトロジーは昨年紹介しましたが。特殊な形のハードCLを睡眠時に装着し、角膜を圧迫することで角膜の形を平らに変化させる屈折矯正法です。角膜の形状が変わることで焦点を後方にずれ、しかもレンズを外しても一定時間はその形状が続くので、日中も眼鏡やCLなしで良好な裸眼視力が得られます。さらに、近視の矯正が得られるだけでなく、近視進行をおおよそ32%〜63%抑制することがわかっています。そこで、大人の管理のもとで年齢の低い子どもで近視の進行抑制の方法として選択されるようにもなっています。ただし、就寝中のCL装用は適切な処方や管理を怠ると角膜感染症など失明につながる重篤な合併症があるので管理が大切です。
5)レッドライト治療
2014年に偶発的に、中国で長波長(650nm)の赤色光が過剰な眼軸伸展を抑制することが発見されました。 アメリカ眼科学会雑誌に、この治療法の非常に高い近視進行抑制効果が発表されて話題となりました。650nmの赤色光というのはいわゆる可視光なのですが、治療は専用の器械を用いて1回3分、1日2回、自宅で週に5回覗き込むだけというものです。 忠実に実行した場合に近視進行が約9割抑制されたという結果でした。現時点では単独で最も優れた治療ですが、長期的な安全性にはさらなる研究成果が待たれます。