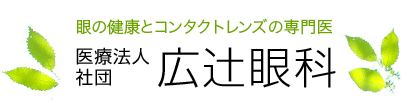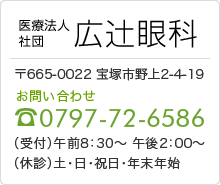白内障手術後の注意点と合併症
院長 廣辻徳彦
白内障手術は現在日本で一番多く行われている外科的手術で、令和元年度で約160万件の手術が行われています。私が医師になった約40年前は、1週間程度の入院、手術後は頭部を固定して3時間のベッド上安静、数日は眼帯を装用するなど多くの制限がありました。現在は原則入院がいらない手術になり、手術後の制限も少なくなりました。ただ、手術後に気をつけるべきことや手術後に生じる合併症などは変わらず存在しています。今回は一般的な生活の注意点や白内障手術の「術後合併症」についてご紹介します。
クリニックや病院で差はありますが、手術の創口(=傷口)を守るためにいろいろな制限を行います。手術後すぐ(眼帯を外したあと)であっても、ものを見ることに制限はかけません。しかし、白内障手術では創口を縫合しないので、物理的に擦ったり圧迫したりすることは避けるべきです。具体的には(短い期間ですが)術後に眼帯をしたり、洗顔や洗髪後にタオルで眼の周囲を拭くことなどを制限したりします。眼帯をせず保護眼鏡のみで帰宅させるクリニックもありますが、年齢などによって制限を実行できるかには個人差があります。当院では、術翌日の診察までは眼帯を装用(以後は保護眼鏡)、翌日を含む4日間は洗髪、洗顔を不可としています。点眼薬については抗菌薬を3週間前後、抗炎症薬を1ヶ月あまり使用していただいています。次は手術後の主な合併症です。
術後の屈折誤差:手術前にどの程度の屈折値(近視や正視など)にするかの予定を立てます。最新の器械を使用してもある程度の誤差は避けられないのですが、その予想値との誤差が大きくなってしまうことがあります。その場合は眼鏡などでの調整が必要となります。
術後眼内炎:手術した創口から最近が眼内に入り込み引き起こされる感染症です。多くは術後2−3日をピークとして1週間以内に発症しますが、術後1ヶ月を過ぎて発症するケースもあります。痛みや充血を伴うことが多く、視力の低下を伴います。早期発見と早期治療が重要で、抗菌薬で治療し、症状が強い場合には眼内レンズの抜去まで含めて手術を行う場合もあります。
後発白内障:手術の際、眼内レンズはもともとの水晶体の内部にあるタンパク質を除去した後、残した水晶体嚢(水晶体の袋だった部分)の中にはめ込みます。後発白内障とは、眼内レンズの後方にある袋の内部に残っている細胞が増殖して袋の膜が濁り、視力が低下する病気です。症状が出ないものを含めると数割に発症します。視力が低下した場合は、YAGレーザーという装置で混濁した膜を破る日帰りの処置で治療します。
眼内レンズの位置異常:手術後に眼内レンズが元の位置からずれてしまう状態です。手術月問題なく終了しても、水晶体を支えているチン小帯(毛様小帯)というところが弱い場合に生じます。手術後数年以上経過してから起こることもあります。少しのずれであれば症状が出ませんが、大きくずれたりまったく元の位置から外れてしまったりすると、視力が低下します。眼内レンズを元の位置に戻す手術、新しいレンズを眼球に固定する手術が必要になります。
眼圧上昇:手術後の炎症などで一時的に眼圧が上昇することがあります。稀にそれが持続することもありますが、多くは点眼薬での治療で正常化します。
角膜内皮障害:手術の際は角膜の切開が必要なため、角膜の一番内側にある内皮細胞がわずかに減少します。もともと内皮細胞が少ない場合や手術中に何らかの問題が生じた場合、内皮細胞の減少割合が多くなり、「水疱性角膜症」という角膜が濁る病気になることがあります。混濁の程度が強い場合には角膜移植が必要になります。
網膜剥離・黄斑浮腫:もともと網膜に薄くなっている部分がある場合、手術の影響でそこに裂け目ができて網膜剥離が生じることがあります。また、手術そのものの炎症や顕微鏡の光の影響で網膜の中心にある黄斑部に浮腫(むくみ)が起こることがあります。網膜剥離は手術で、黄斑浮腫は点眼などで治療します。
何らかの治療が必要な処置以外に、濁った水晶体を透明な眼内レンズに入れ替えることで明るい光が入り込み、飛蚊症が増えたという症状を自覚されることがあります。ほとんどは時間の経過で気にならなくなりが、比較的多く現れます。光の入り方によって眼内レンズに中で光が屈折し、視界の端の方でキラッと光る感じを自覚されることもあります。
白内障の手術後、長期間にわたって毎月受診する必要はありませんが、自覚症状が少ない病気が起こっていることもあるので、1年に1度くらいは受診されておくのがよいと思います。