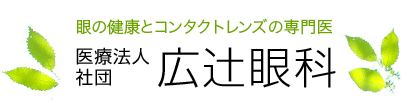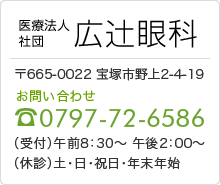ぶどう膜炎について(その2)
院長 廣辻徳彦
前回はぶどう膜という眼の部分を紹介し、ぶどう膜炎という病気があることやその種類を書きました。今回はぶどう膜炎の代表的なものと、その治療法などについて説明します。ぶどう膜炎の原因は、免疫異常が主な原因となる「非感染性ぶどう膜炎」と、病原菌やウイルスの感染が原因となる「感染性ぶどう膜炎」とに大別されます。「非感染性ぶどう膜炎」には、3大ぶどう膜炎とも呼ばれるサルコイドーシス、原田病(フォークト・小柳・原田病)、ベーチェット病という病気などがあり、本来身体を守るための免疫系が誤ってぶどう膜の組織を攻撃して炎症を起こすと考えられていますが、3分の1程度は原因がわからないとされています。
サルコイドーシスは原因不明の多臓器疾患です。眼以外では肺、皮膚、心臓、神経、骨、筋肉などいろいろな臓器に肉芽種(にくげしゅ)性といわれる病変を形成することがあります。肉芽種とは、身体の防御反応として炎症を起こしている部分に免疫細胞が集まってできる炎症性のしこりのようなものです。20代と50代以降に発症することが多く、高齢では女性に多いことが知られています。眼科を受診して、特徴のあるぶどう膜炎の状態から全身の検査を行ってサルコイドーシスの診断につながることもあります。胸部X線写真でのリンパ節腫大、血液検査や心電図検査での異常や、皮膚や結膜にできた結節の組織を検査して診断がつくこともあります。ぶどう膜炎に対しては、ステロイド薬の点眼が主で、重症度によってはステロイド薬の内服も行われます。
原田病(フォークト・小柳・原田病)は20 〜40 代に発症が多い病気で、日本人を含む東洋人に多く発症します。身体の組織にある「メラノサイト」という色素細胞に対する自己免疫性疾患と考えられています。ぶどう膜炎症状は虹彩炎のほかに、視神経乳頭の発赤や網膜下に滲出液がたまる網膜剥離が生じます。治療後(経過後)の眼底は、網膜が赤っぽく見える「夕焼け状眼底」という状態になることもあります。全身的には、眼症状に先立って感冒様症状、頭痛、頭髪の感覚異常、難聴、耳鳴りなどが起こることがあり、回復期には皮膚の白斑、白髪化、脱毛などの変化が起こります。治療は全身的な大量のステロイド治療が用いられ、再発を繰り返す場合には免疫抑制剤なども使われます。原田病によく似た病態を示すぶどう膜炎に「交感性眼炎」という病気があります。これは穿孔性眼外傷(眼球に孔があくような外傷)や内眼手術(網膜剥離などの手術)の後、「外傷や手術をしていない方の眼」にぶどう膜炎が生じるもので、治療は原田病と同じように行います。
ベーチェット病は以前に比べて報告数が少なくなっていますが、重要な疾患です。眼には充血などを伴う虹彩炎や脈絡膜炎、網膜炎や、前眼部蓄膿という特徴的な症状が出現します。この眼症状と「口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍」、発赤と硬結(皮膚の下が硬く触れること)に痛みを伴う皮疹(結節性紅斑)という「皮膚症状」、「外陰部潰瘍」をベーチェット病の4主徴と呼んでいます。他にも関節炎、消化器症状、神経症状、血管炎など多彩な症状が現れます。これらの症状は一度に出るわけではなく、長い経過の中で出てくることもあるため、診断までに時間がかかることがあります。眼については、「発作」と呼ばれる強い炎症が急に出現することもあり、網膜などに強い炎症を繰り返した場合、視力が極端に低下(最悪失明)することもあります。ベーチェット病を完全に治す治療法はありませんが、眼症状についてはステロイドの局所投与(点眼や注射)、免疫抑制剤やコルヒチン、最近ではインフリキシマブやアダリムマブという生物学的製剤を組み合わせて行います。生物学的製剤の使用ができるようになって、失明するほどの事例が少なくなっているようです。
他にも非感染性ぶどう膜炎には、急性前部ぶどう膜炎、HLA-B27関連ぶどう膜炎、フックス虹彩異色性虹彩毛様体炎、ポスナー・シュロスマン症候群 、糖尿病虹彩炎などがありますが、ステロイドの点眼や眼局所への注射や全身投与、免疫抑制剤、生物学的製剤などが用いられます。
「感染性ぶどう膜炎」は、単純ヘルペス、水痘・帯状疱疹ヘルペス、サイトメガロウイルスというヘルペス属のウイルスや、細菌、真菌(カビなど)や結核菌、梅毒、ヒトT細胞白血病ウイルス1型, トキソプラズマ(ネコに関連する原虫)の感染などで起こります。感染が起こる場所によって、虹彩炎や脈絡膜炎、網膜炎、血管炎や出血、なかには網膜剥離(増殖網膜症)などの所見を呈します。病原体によっては、特徴的な所見を示すものもあります。感染性ぶどう膜炎の場合、まずは感染の原因となる病原体に対する抗菌(抗ウイルス)薬の投与を行います。病原体によって薬が異なるため、確定診断のために血液検査で血清抗体価や眼球内の液体のサンプルから病原体を調べることもあります。炎症症状を抑えるためにステロイド薬などを用いる事もあり、網膜剥離を起こしている(起こしそうな)場合などには手術的治療を行います。