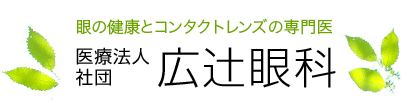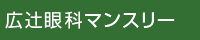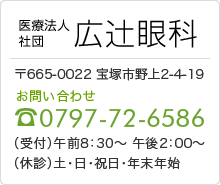1年を振り返って
院長 廣辻徳彦
早いものでもう12月、1年の終わりの月です。今年も終わりということで、10大ニュースというわけではありませんが、今年よく耳にした話題を順不同で考えてみました。関西では、「大阪万博」を挙げるべきではないでしょうか。当初はパビリオンの建設が間に合わない、予約が難しいなど不安材料が取り沙汰されたところもありましたが、キャラクターのミャクミャクのおかげか徐々に人気が高まって、最終的には2500万人以上が来場し、なんとか黒字の決算になったようです。数年前に少しだけでも買っておけばよかった、と思わされたのが「金相場の高騰」です。今年の初めには14,700円台だった1gの価格が現在は約23,000円になっています。10年前の価格は4,500円、20年前は2,000円だったので、持っている人はホクホク顔をしていらっしゃることでしょう。ただ、金はこれまで採掘された総量が約19万トンでオリンピックプールの3.5〜4杯分、残っている埋蔵量は約5万トンと言われています。いつまでも採掘できる資源ではないようです。政治の世界では石破首相の退陣、高市新首相の誕生、自民党と公明党との連立解散があって維新の会との新連立が成立など、夏の終わり頃から大きな動きがありました。高市首相は外交デビューがそれなりに評価されたと思った矢先、台湾有事に関する発言が中国政府を刺激して問題になっています。かの国の政府の言うことはほとんど「イチャモン」に近く、一方的に作られている外交問題というレベルなのですが、キャンセルされた観光先には気の毒なことです。ただ、京都であまりに多い○国からのお客さんに閉口した経験からは、オーバーツーリズムが少し解消するといいような気もします。また、今年は市長や知事が不倫騒動やセクハラ、パワハラで辞任に追い込まれることも増えた気がします。大雨被害が九州や東北、八丈島で発生しました。線状降水帯の発生はわかるようになりましたが、実際に大雨が降ると安全なところに避難する以外方法がありません。先月には佐賀関での大火事に続いて香港でマンション火災がありました。改めて防災への意識を高めなければならないと実感します。スポーツでは大相撲で大の里が横綱になり、ウクライナ出身の安青錦が大関になりました。ノーベル賞を日本人が2人受賞したのもうれしいニュースです。どうしても暗い話題が多くなる傾向がありますが、来年はいいことが次々駆けていくような午年になって欲しいものです。
ちなみに私にとってだけであれば、3人目の孫の誕生がナンバーワンの出来事でした(かわいいです)。
健康とは!(数字が語る、この季節の注意点)
冬の気配が近づいてきたこの頃ですが、昼間はまだ気温が高く本格的な冬が始まったという感じではありません。空気が冷たくなってくるのと同時に、体調管理にも気が引き締めないと思うようになってきます。特に今年はインフルエンザの流行が例年よりも早く、しかも勢いよく拡大しています。インフルエンザの流行の指数として、全国の指定医療機関での1週間あたりの報告数を厚労省が毎週発表しています。この報告数が1.0を超えると流行の開始の目安になるとされています。例年では、11月末から12月ごろに1.0を超えることが多いとされています。ところが今年は10月初めに1.0を超えたので、すでに流行が始まっていると考えられています。注意報レベルと言われるレベルは報告数10を超えるところと定義されていますが、10月末から11月はじめの週に10を超えてしまいました。11月半ばには警報レベルの30を超え、一番最近の11月末の報告では50を超えています。ちなみに、昨年の24−25シーズンの場合を振り返ると、12月に入った時には報告数が10に満たない程度だったものが、正月にかけての3週で60を超える急激な流行を示しました。ただ、このシーズンの流行は正月末にほぼ10にまで下降するという比較的短めの流行で済んでいます。その前の23−24シーズンは、ピークこそ報告数30程度の流行でしたが、10を超えていた期間が10月半ばから3月末までといった少し長めの流行であったようです。例年より早く始まり急速に拡大している今年の流行のピークがいつになり、いつごろまで続くかはまだわかりませんが、空気が乾燥して感染が広がりやすい時期はこれからです。インフルエンザも油断できない病気であることは明白でので、感染の予防には気をつけなければなりません。
それでは、感染への備えとはどうすればいいのでしょう。インフルエンザの感染予防には、日常での基本対策が重要です。外出後や食事の前後にこまめな手洗いやアルコール消毒を行い、ウイルスを体内に持ち込まないようにしましょう。コロナ感染の収束以降マスクをする機会が減りつつありますが、混雑した場所ではマスクの着用が効果的です。また、「うるおい」が大事なので、室内は加湿と換気を心がけ、乾燥を防ぐことでウイルスの広がりを抑えられます。栄養バランスの良い食事と十分な睡眠で免疫力を保つことも大切です。抵抗のある方もいらっしゃるでしょうが、毎年の予防接種には重症化を防ぐ効果があることが認められています。これらの対策を組み合わせ、感染を予防してお正月を迎えましょう。