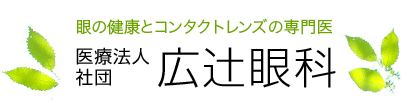瞳の大きさが違います(瞳孔不同について)
院長 廣辻徳彦
今回は瞳(ひとみ)の大きさについて考えてみます。瞳には正しくは「瞳孔」という名前がついていて、東洋人では茶目とか黒目とかの色の元となっている「虹彩」の中央部、ドーナツの穴のように開いているところです。光学的カメラでは「絞り」に相当し、眼の中に入ってくる光の量を調節しています。瞳孔は明るい場合には小さく(=縮瞳)なり、暗いところでは大きく(=散瞳)なります。縮瞳には瞳孔括約筋という筋肉が作用し、動眼神経という神経の中を通る副交感神経によって支配されています。散瞳には瞳孔散大筋という筋肉が作用し交感神経に支配されています。交感神経や副交感神経はいわゆる「自律神経」と言われるもので、自分の意志で作用させることができない神経です。瞳孔径(=瞳孔の大きさ、直径)は2.5-4mm程度で周囲の明るさによっても変動し、加齢によって小さくなる傾向にあります。

瞳孔に働く自律神経の異常や光を感じる視神経に異常があると瞳孔の大きさに左右差ができることがあります。こういう場合を「瞳孔不同」と呼んでいます。逆に考えれば瞳孔不同がある場合には、何らかの神経の異常を疑うことができるわけです。今回は瞳孔不同を起こす状態や疾患について、眼球に原因がある場合とそれ以外の場合に分けて書いてみます。
図;白丸の内部が瞳孔(瞳:ひとみ)
眼球に原因がある場合の中で、生まれつき左右の瞳孔径が違う状態が「生理的瞳孔不同」です。1-2割くらいの人にあるのですが、病気ではありません。自覚症状はなく、ほとんどが0.6mm以内の差で1mmを超えることはないようです。虹彩に何らか病気や刺激が生じた時に瞳孔異常が起こります。「外傷」の中で鈍的外傷といって殴打されたりボールが当たったりした場合に、打撲が治っても瞳孔が散大気味になって戻らないことがあります。白内障や網膜剥離などの「手術後」でも瞳孔の大きさに変化が出ることがあります。「虹彩炎やぶどう膜炎」という病気では虹彩そのものが病気になるので、罹患中に瞳孔の大きさに異常が出ることがあります。炎症の程度が強い場合には、瞳孔縁と水晶体の間で炎症による癒着が生じて瞳孔の形がいびつになってしまうこともあります。「急性緑内障発作」で急に眼圧が上がった場合、治療が終わった後も瞳孔が散大気味になることもよくあります。虹彩に異常がなくても、「視神経炎」という病気では瞳孔が開き気味になります。視神経を介して光(明るさ)の情報が中枢に伝わって瞳孔の大きさが調節されているので、視神経炎が起こった眼(もしくは悪い方の眼)と病気のない眼(もしくはましな方の眼)との間で光の入力のバランスが悪くなってしまうという理由です。視神経炎でも両眼が同じ程度で障害されているのであれば、光の入力に差がないので瞳孔の大きさにも差は出ません。「片方の眼の網膜が広範囲で障害」された場合、例えば網膜剥離などの病気で手術の甲斐なく視力がもどらなかったという時にも、その眼からの光の入力が悪くなって瞳孔の大きさに差が出ることがあります。
眼球自体に問題がない場合、瞳孔を動かす神経の異常などでも瞳孔径に差がでます。副交感神経を含んでいる動眼神経の異常である「動眼神経麻痺」では瞳孔が散大します。この場合は眼球が外を向き(外斜視:複視の症状が出ます)、眼瞼下垂も生じます。動眼神経麻痺は糖尿病などが原因の一過性のものも多いのですが、脳動脈瘤の圧迫が原因になることもあるので、必ず脳外科的検査が必要になります。交感神経に異常が出た場合には縮瞳気味になります。「ホルネル症候群」と言って、縮瞳とともに眼瞼下垂や同じ側の顔面の発汗の低下が見られます。脳から出た交感神経には、一度脊髄の中を通って胸部で脊髄を出て頚動脈の付近を通って頭部に戻り、頭蓋骨の中を通って眼にいたる経路を持つものがあるので、その経路のどこかで交感神経が障害された場合にこの病気が起こります。肺がんや他の腫瘍、リンパ節の腫脹、大動脈解離や胸部大動脈瘤などが原因になることがあるので注意が必要です。「アディー(Adie)症候群」という病気では、片方の瞳孔が散大気味になります。原因はよくわからないことが多いのですが、対光反応(光をあてると瞳孔が小さくなる現象)がほとんど減弱しているのに、近見反応(寄り目)をさせるとわずかずつ縮瞳するという反応を見せます(アキレス腱反射や膝反射の消失なども伴います)。他にも、「脳梗塞や脳出血」で瞳孔径に異常(+眼球偏位)が出ることもあります。
たった4mm程度の大きさの瞳孔ですが、その大きさの差や対光反応の異常がきっかけで大事な病気を見つける窓口になることもあるのです。